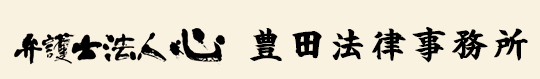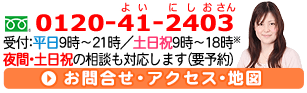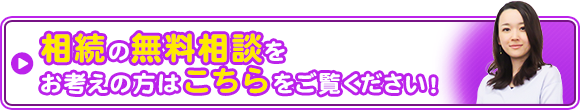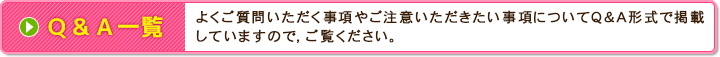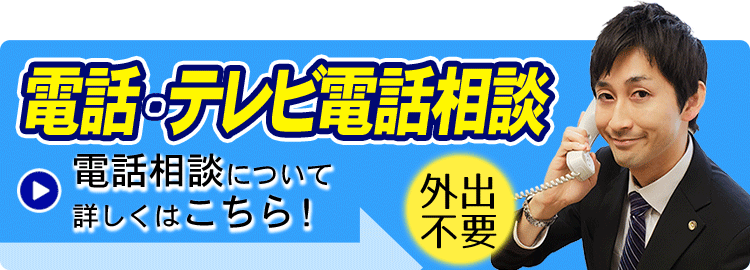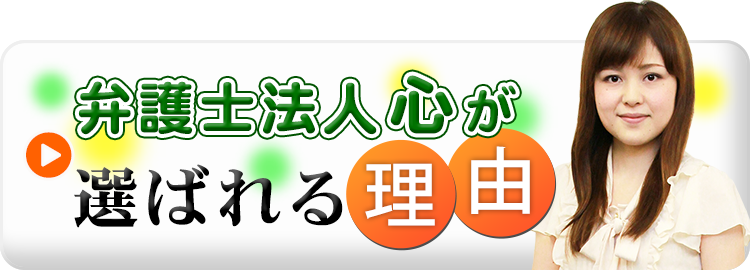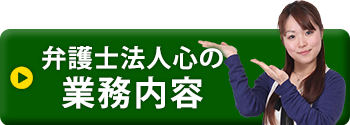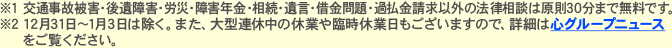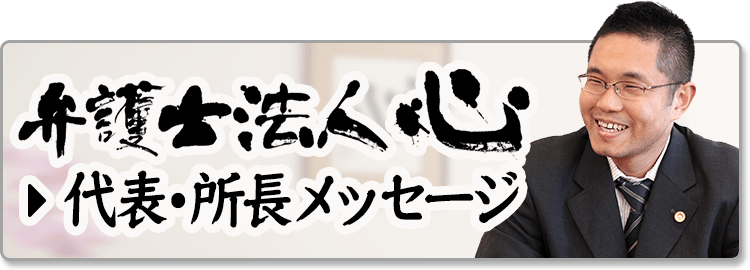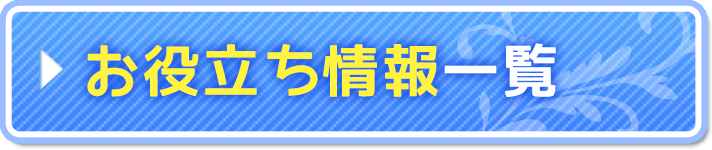相続手続きの流れと期限
1 相続手続きの流れ
相続手続きの流れは、多くの場合、最初に、遺産分割協議等により遺産分割の方法を確定し、次に、個々の財産の払戻、名義変更を行うというものとなります。
また、被相続人の負債が多額である等の理由で相続放棄を行う場合には、家庭裁判所において相続放棄の申述の手続きを行うこととなります。
2 遺産分割方法の確定
⑴ 協議による遺産分割方法の合意
遺産分割方法を確定するにあたっては、まずは、相続人全員で協議を行い、遺産分割方法について合意を試みることとなります。
遺産分割方法を確定するにあたっては、どの財産を誰が引き継ぐかを決めたり、財産を引き継ぐ代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うことを決めたりします。
相続人全員の合意が成立すれば、合意内容を遺産分割協議書の形式でまとめ、相続人全員が署名、押印することとなります。
後日、遺産の払戻、名義変更を行う必要があることが多いため、遺産分割協議書については、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付するようにしてください。
⑵ 協議で遺産分割方法の合意ができない場合
他方、協議により遺産分割方法を確定することができなかった場合には、弁護士等の専門家が他の相続人との意見を調整したり、遺産分割調停等の法的手続きを利用したり等の方法を用いて、解決を図ることとなります。
基本的には、遺産分割方法を確定するにあたり、定まった期限はありません。
もっとも、時間が経てば経つほど、相続人間の交渉が困難になったり、相続人数が増加したりして、解決が困難になることが多いため、いつまでも未確定のままにしておくことは、望ましいことではないと言えます。
また、遺産に含まれる不動産を売却する際には相続人全員の関与が必要となりますので、債務の返済等のために早期に不動産を売却する必要がある場合には、早期に相続人間で合意を成立させる必要があります。
さらに、相続税申告が必要な場合で、当初申告の段階から小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減等の制度を用い、相続税の納付額を減額することを希望する場合には、相続税の申告期限である、相続を知った時から10か月までに遺産分割の方法が確定している必要があります。
このような事情がある場合は、早期に遺産分割方法を確定しておく必要性が大きいと言えます。
⑶ 寄与分や特別受益の主張の期限にも注意
相続開始から10年経過してしまうと、原則として遺産分割において寄与分や特別受益の主張ができなくなってしまいます。
そのため、こうした主張がある場合はご注意ください。
3 払戻、名義変更
⑴ 払戻、名義変更の手続き
遺産分割方法が確定すると、その内容に基づき、不動産、預貯金、有価証券等について、払戻、名義変更の手続きを行うこととなります。
不動産については法務局において、預貯金については各銀行において、有価証券については各証券会社において、手続きを行うこととなります。
⑵ 相続登記の期限に注意
預貯金と有価証券の手続きについては、定まった期限はありませんが、相続登記については2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならないことになります。
これまでに相続した不動産についても、2024年4月1日から3年以内に登記を行うことが必要です。
もしも遺産分割がまとまらない等の理由で期限内に相続登記ができない場合には、いったん法定相続割合で登記をするか、法務局に相続人であることを申し出て、登記の期限を延長してもらうという制度を利用することも可能です。
⑶ 期限がないものも早めの対応が必要
これらの手続きを行うには、遺産分割協議書等の書類が揃っている必要があります。
書類はそのままにしておくと散逸するおそれがありますので、期限が定められていないものについても、早めに手続きを行うのが望ましいと言えます。
印鑑証明書については、銀行、証券会社では、3か月から6か月が有効期限とされていることがほとんどですので、印鑑証明書の有効期限が経過する前に手続きを行う必要があります。
不動産について遺贈の登記を行う場合も、印鑑証明書の有効期限が3か月になりますので、注意が必要です。
4 相続放棄
相続放棄を行うには、家庭裁判所で申述書を提出する必要があります。
相続放棄に当たっては、被相続人の住民票の除票、被相続人の戸籍(多くの場合、出生から死亡まで)、相続人の戸籍等の書類も提出する必要があります。
また、多くの家庭裁判所は、相続放棄の申述が行われると、申述した相続人に対し、意思確認のために照会書を送付しますので、照会書に対する回答も遅れずに行う必要があります。
申述書の提出については、基本的には、相続を知った時から3か月以内に行う必要があります。
これらの手続きに不備があると、相続放棄の申述が受理されませんので、慎重に手続きを行う必要があります。
どんな相続財産があるのか分からない場合の調査方法 不動産の相続手続きについて