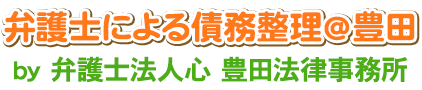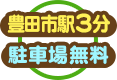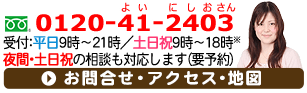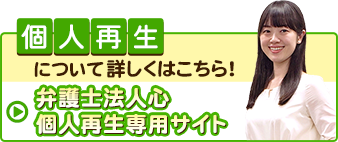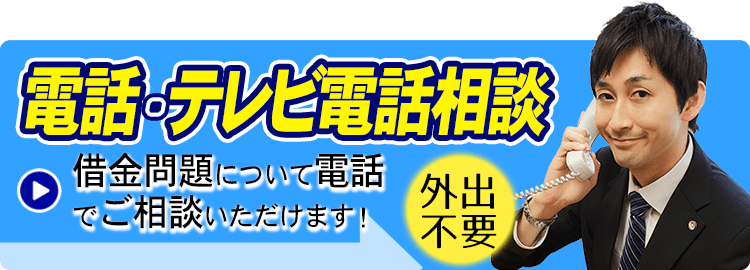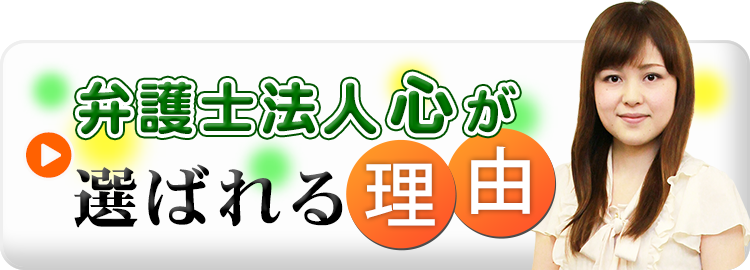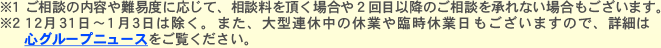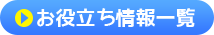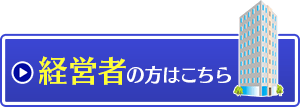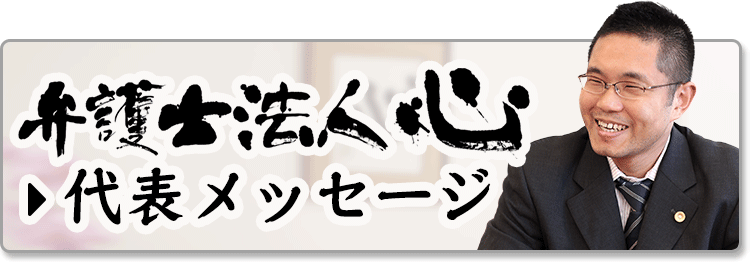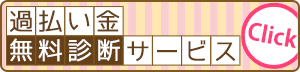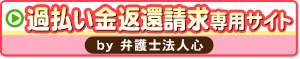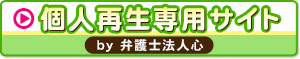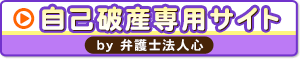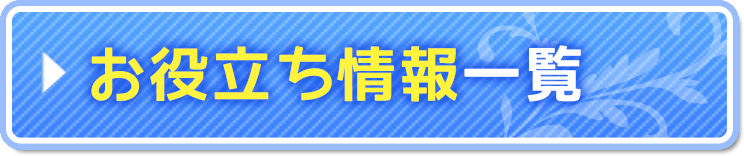個人再生のご相談をお考えの方へ
個人再生は、借金を減額し、かつ分割払いで返済できるようにするための制度です。
個人再生の制度を使うべきかどうかは、財産や収入の状況等によって異なります。
当法人へご相談いただければ、個人再生などの債務整理の案件を集中的に取り扱っている弁護士がしっかりと検討し、適切な方法をご提案させていただきます。
当法人には,債務整理の案件を集中的に取り扱う弁護士が在籍しております。皆様のお悩みをしっかりとお伺いした上で,より適切と思われる債務整理の方法を提案いたしますので,個人再生を行うべきか迷われている方も,お気軽にお話をお聞かせください。
個人再生は手続きが複雑な債務整理だといわれていますが,弁護士にご依頼いただくことでよりスムーズに手続きを行うことができるようになります。お悩みを抱えていらっしゃる方は当法人までご相談ください。弁護士・スタッフ一同ご相談をお待ちしております。
こちらから事務所付近の詳細な地図などをご確認いただけます。当法人の事務所は,お車の運転が難しい方にもお越しいただきやすいよう,すべて駅の近くに設けております。豊田の事務所も駅から徒歩数分の場所にありますので,お気軽にお越しください。
個人再生の手続きの期間
1 個人再生の期間

個人再生を弁護士に依頼した後は、申立ての準備、申立て、開始決定、再生計画案の提出、債権者の書面決議(給与所得者等再生の場合には債権者への意見聴取)、裁判所の認可決定、認可決定の確定の順序で進んでいきます。
個人再生の手続きは、半年から1年ほどかかることが通常です。
2 申立ての準備
個人再生の申立てでは、債務の内容、収支の状況、財産の状況について、資料を付して裁判所に提出する必要があります。
この準備には、2か月から3か月間の収支の状況を作成しないといけないこともあり、3か月から半年ほどかかることが多いです。
ただ、状況によっては急いで申立てをしないといけないこともあり、資料等が揃うのであればより短い時間で申立ての準備を終えることもあります。
3 申立て~開始決定
申立てに必要な資料が揃ったら、裁判所に個人再生の申立てを行います。
申立てを行うと裁判所が資料を精査し、開始決定を出すにあたって不足する資料はないか、追加で確認すべきことがないかを検討し、不足等があれば申立代理人に補充すべき事項を連絡します。
この補充事項に回答する、もしくは、不足する資料や追加で確認すべきことがない場合には、開始決定がなされます。
通常、この期間は1か月から2か月程度かかることが多いです。
4 開始決定から再生計画案の提出
開始決定がなされると、減額された再生債権をどのように支払っていくかを定めた再生計画の案を提出する期限が設定されます。
通常この期限は、申立てから2か月後になることが多いです。
5 再生計画案の提出から書面決議
再生計画案が提出され、問題なければ、小規模個人再生の場合には書面決議に付され、給与所得者再生の場合には債権者からの意見聴取に付されます。
小規模個人再生の場合には、ここで債権者の頭数の半数以上、もしくは債権額の半額以上を占める債権者から反対の意見が出た場合には、再生手続きは廃止となってしまいます。
通常、この期間は1か月ほど取られることが多いです。
6 書面決議から認可決定
書面決議や意見聴取で問題が生じなかった場合には、裁判所が法律上の問題ないかを審査し、問題なければ再生計画の認可を決定します。
通常、この期間は2週間程かかることが多いです。
7 認可決定から確定
認可決定がなされると、その旨が官報に掲載されます。
官報に載ってから2週間が、認可決定に対して問題があるとして債権者等が抗告することができる期間となるので、その期間中に債権者等から抗告がなされない場合には、今後再生計画が覆されることはなくなります。
これを確定といいます。
認可決定から確定までは通常1か月程度かかることが多いです。
確定後から再生計画に従い、返済等を行っていくことになります。
個人再生をした場合の債務額
1 個人再生の債務額について

個人再生は、裁判所に申立てを行い、減額された債務額を3~5年間かけて返済する手続きです。
返済していく債務額が決まる基準は、債務を基準としたもの、財産を基準としたもの、そして可処分所得を基準としたもの(給与所得者等再生の場合のみ)の3つあります。
その中で、一番金額の高いものが個人再生手続きで返済することになる債務額となります。
2 債務を基準としたもの
個人再生では、100万円が最低弁済額と定められており、住宅ローンの返済を続けていく条件の場合には、住宅ローンを除いた債務が100万円を下回る場合、債務額は全額となります。
そして、債務が100~500万円の場合は100万円、債務が500~1500万円の場合は5分の1に減額された金額、債務が1500~3000万円の場合は300万円、債務が3000~5000万円の場合は10分の1に減額された金額が債務額となります。
なお、債務が5000万円を超える場合は、個人再生の対象外となり、通常民事再生という手続きを行う必要があります。
3 財産を基準としたもの
個人再生では、財産の総額も最低弁済額の基準となります。
財産には、預金、現時点で解約をした場合の保険解約返戻金、自動車、不動産、現時点で勤務先を退職した場合の退職金、家財道具、友人等にお金を貸している場合の債権といったものが含まれます。
財産の評価方法は複雑であり、個々の事情を踏まえて判断することになりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
4 可処分所得を基準としたもの
個人再生における可処分所得は、年収から、税金・社会保険料、個人再生手続きを行う方や扶養家族の最低限度の生活費を差し引いて計算します。
一般的に、債務や財産を基準とした債務額よりも可処分所得の方が高額になる方が多く、特に収入が高い方や、扶養家族がいない方などは、高額になる傾向にあります。
返済額が予想以上に高額になると、方針変更も検討せざるを得ない可能性もありますので、給与所得者等再生を行う場合は、早期に可処分所得を算出しておくのが望ましいといえます。